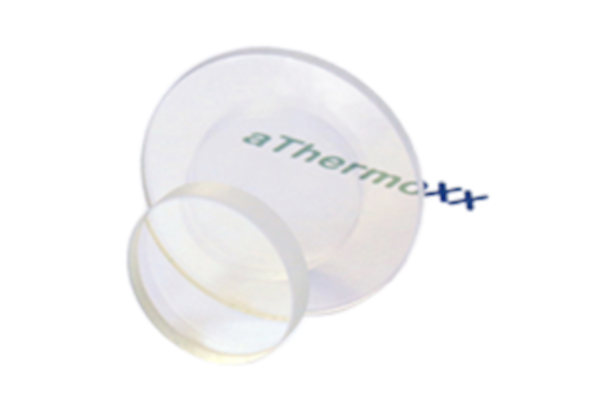マルチフォーカスレンズ

光軸方向に複数の集光スポットを同時に生成するレンズです。
屈折型の熱レンズ効果抑制光学素子で構成されており、熱レンズ効果が起きにくく、また透過率が高いというのが特徴です。
この光学部品には、調整機構がありスポットの数やパワーバランスの調整が可能です。

へえ、屈折型の光学部品でマルチフォーカスができるんだね。
DoEでやるもんだと思ってた。
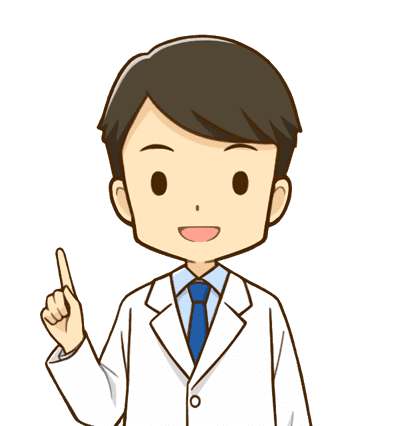
特殊な光学部品で作られていますので、屈折光学系でこれを実現しています。
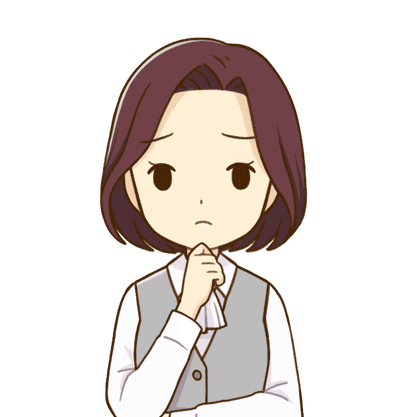
でも、DoEでマルチフォーカスするのと何が違うの?
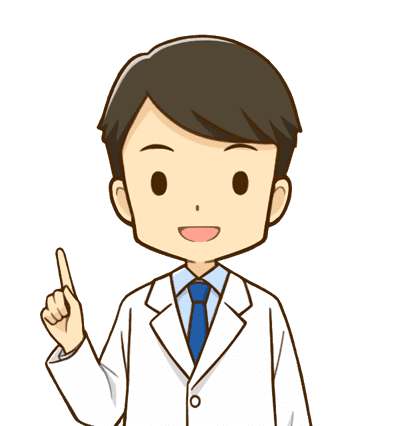
DoEの場合、マルチモードでは効率が悪くなってしまいます。
屈折光学系の場合はシングルモードでもマルチモードでも対応可能です。
いずれにしても、屈折光学系はロスが小さいのでハイパワーのアプリケーションではとても有効ですよ。
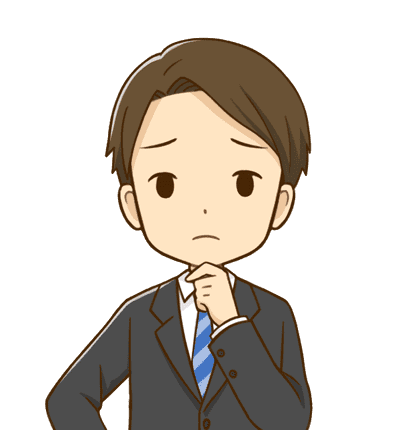
調整可能って書いてるけど、マルチフォーカスを可変できるってこと?
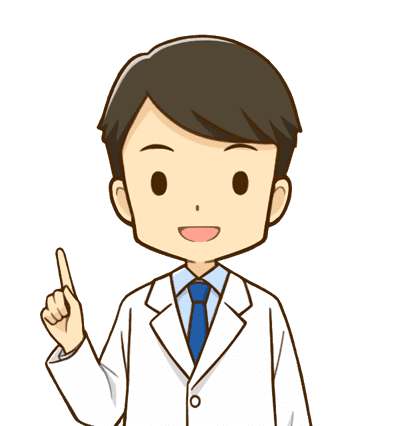
この製品は光軸方向に4点分岐します。それぞれをA、B、C、Dとした場合、調整リングを回すことで、A-D、B-C、A-B-C-Dのように分岐数を変えることができます。
詳しくは以下の図をご覧ください。
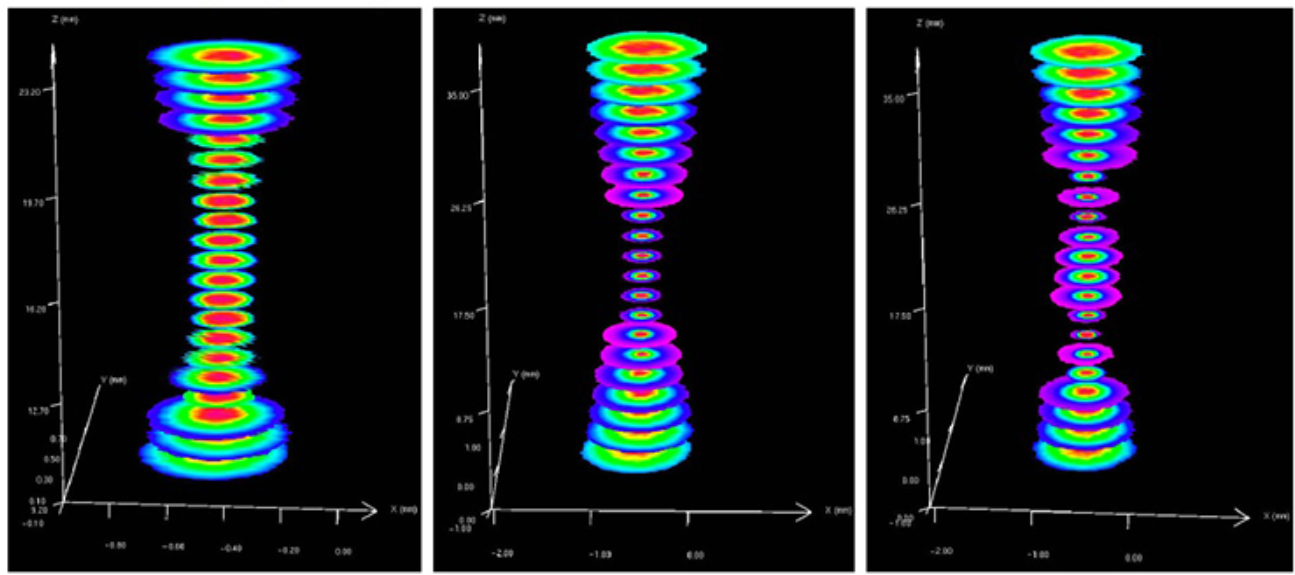
左)2分岐(B-C)、中)4分岐(A-B-C-D)、右)2分岐(A-D)
以下のデータは集光しているビームのレイリー散乱光を横からカメラで撮影したものです。左は一般的な集光ビーム(1つのフォーカス)、右はマルチフォーカス光学系を使い、4つのフォーカスを作ったものです。長手方向に均一な集光ができていることがわかります。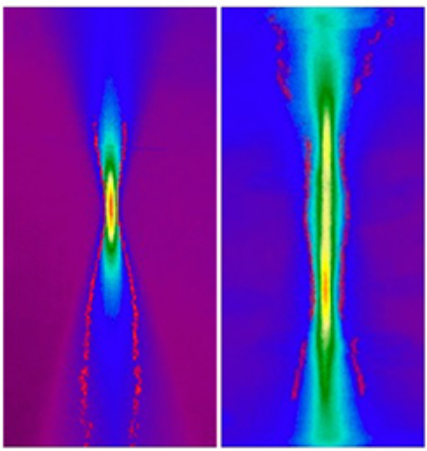

長手方向に強度分布が均一だからプロセスウインドウが広がるね!
集光レンズとして使用できるものと、コリメータとして使用できるものがあります。
コリメートタイプを使用した場合、マルチフォーカス光学系から出射したビームを一般的な集光レンズで集光すると複数の焦点が得られます。
以下図のように集光レンズとしてご利用いただけます。
入射したビームを最大4つに分岐します。調整リングを回転させることで分岐パターンを変えることができます。
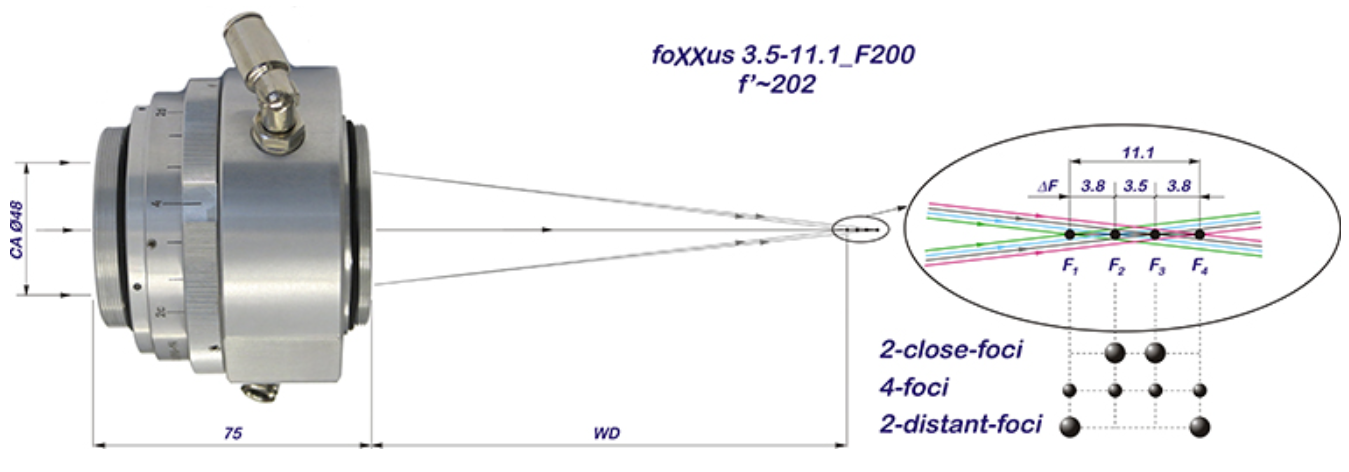
| 共通仕様 | |
|---|---|
|
クリアアパーチャ |
Φ48mm |
|
入射ビーム許容角度 |
±1度 |
|
推奨最大パワー※1 |
6kW CW |
|
マウント |
M58 x1(入出射) |
|
冷却 |
水冷 6-1/8フィッティング |
|
直径 |
90mm |
|
長さ |
75mm |
| 個別仕様 | foXXus_3.5-11.1 F200_NIR | foXXus_3.5-11.1 F200_1064 |
foXXus_3.5-17.4 F250_NIR |
|---|---|---|---|
|
波長(ARコートの波長) |
920-1100nm |
1020-1100nm |
1020-1100nm |
|
ΔF(大気中) |
2焦点:3.5mmまたは11.1mm |
2焦点:5.4mmまたは17.4mm |
|
|
4焦点:3.8 - 3.5 - 3.8mm |
4焦点:5.7 - 5.4 - 6.3mm |
||
|
焦点距離 |
約202mm(197-208.5mm) |
約252mm(243.5-261.6mm) |
|
|
ワーキングディスタンス |
158.5-169.6mm |
205.1-222.5mm |
|
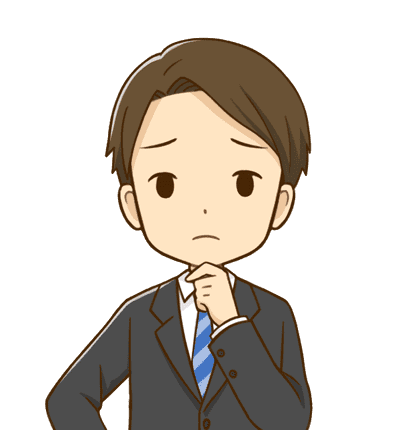
ΔFってなんのパラメータ?
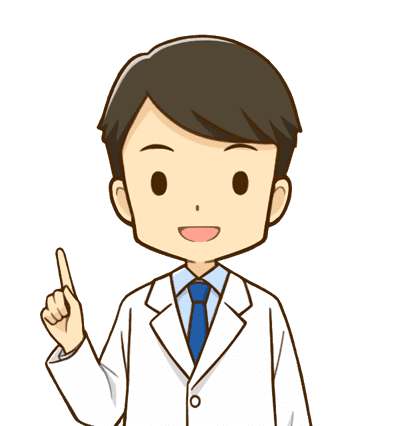
ΔFは生成される集光スポット間の距離です。マルチフォーカスレンズの焦点距離により異なるスポット間距離となります。
以下図のようにコリメータとしてご利用いただけます。コネクタはQBH/QDいずれも対応可能です。
入射したビームを最大4つに分岐します。調整リングを回転させることで分岐パターンを変えることができます。
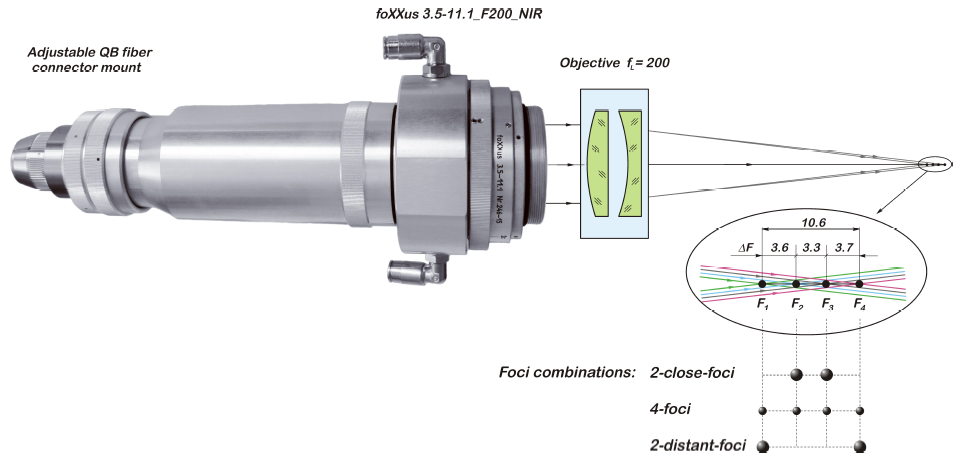
| 共通仕様 | |
|---|---|
|
波長(ARコートの波長) |
920-1100nm |
|
入射ビーム許容角度 |
±1度 |
|
推奨最大パワー※1 |
6kW CW |
|
冷却 |
水冷 6-1/8フィッティング |
| 個別仕様 | foXXus_3.5-11.1 F200_NIR |
foXXus_2-6 F100_NIR |
|---|---|---|
|
焦点距離 |
約202mm(197-208.5mm) |
約101.5mm(98-104.9mm) |
|
ΔF(大気中)※2 |
2焦点:3.5mmまたは11.1mm |
2焦点:2mmまたは6mm |
|
4焦点:3.8 - 3.5 - 3.8mm |
4焦点:2 -?2 - 2mm |
|
|
クリアアパチャ |
48mm |
29mm |
|
マウント |
入射側: QBHコネクタ※3 出射側:M58×1 外ネジ |
入射側: QBHコネクタ※3 出射側:M47×0.75 外ネジ |
|
直径 |
90mm |
67mm |
|
長さ |
288mm※4 |
178mm※4 |
| ※1: 推奨値です。更に高出力での使用ができるものもございます。 | ||
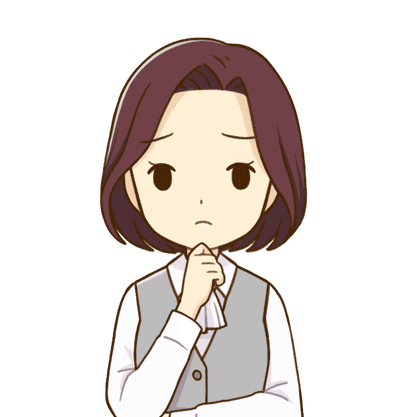
集光レンズタイプはΔFが固定だったけど、コリメータタイプはどうなるの?
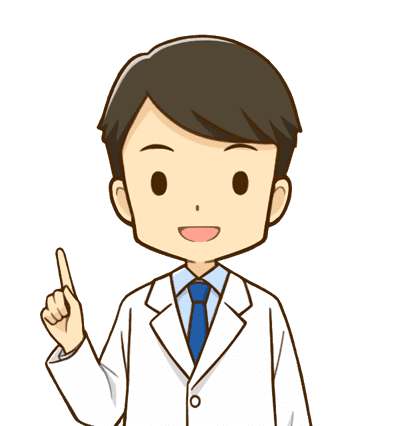
コリメータタイプの場合、ΔFは各機種が持つ固有の値と、使用する集光レンズの焦点距離で決まります。
例えばfoXXus_3.5_11.1_F200_NIRの場合は、焦点距離202mmの集光レンズを使用した場合、各スポット間の距離は、3.8mm, 3.5mm, 3.8mmです。
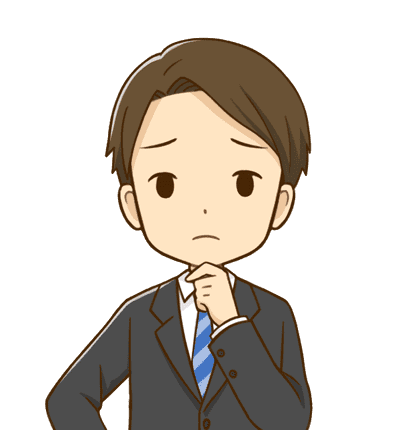
でも必ずしもf=202mmの集光レンズを使うとは限らないよね。
別のレンズを使った場合はどうやって計算すればいいの?
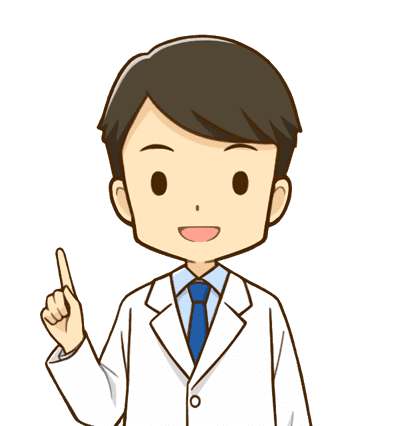
基準となる焦点距離、基準となるΔFは仕様に書かれている通りです。
もし、焦点距離を202mmではなく、半分の101mmにした場合、スポット間距離は、仕様書にある基準値の(101÷202)^2=1/4になります。
焦点距離比率の2乗で効いてくると覚えてください。